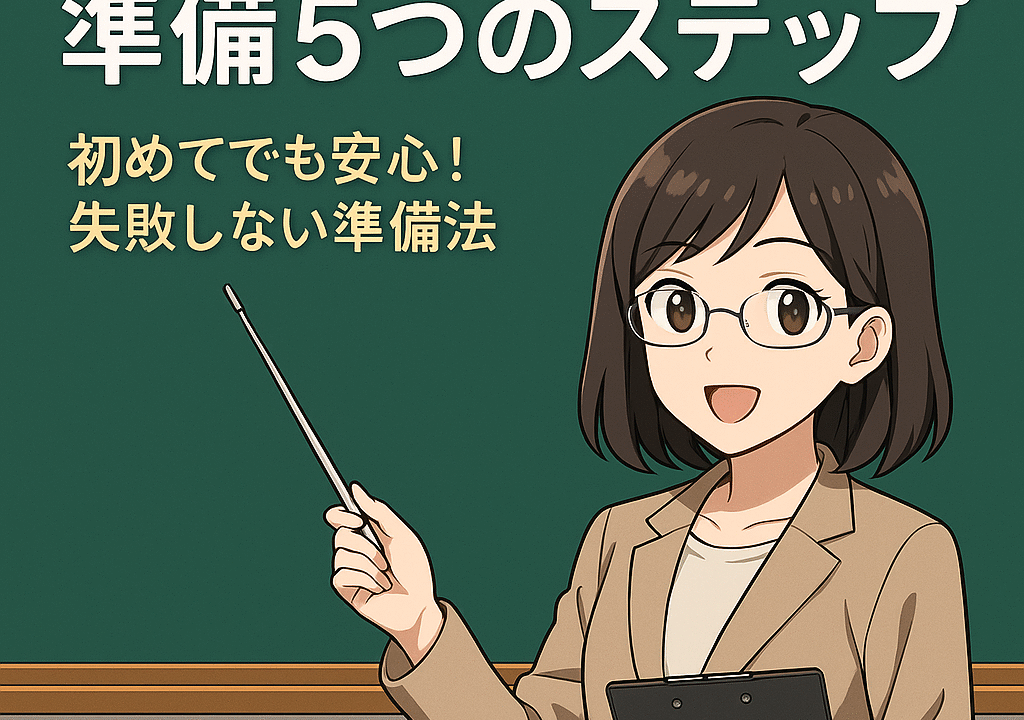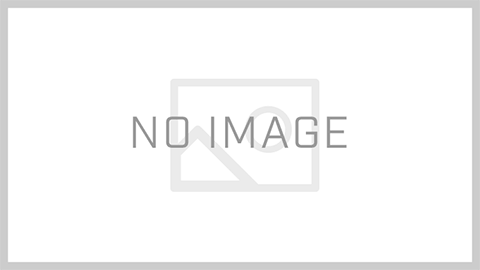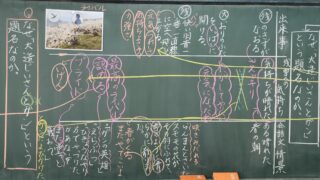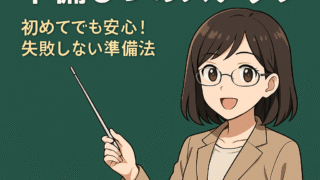ー初めてでも失敗しない、小さく始める方法ー
「自由進度学習に興味はあるけれど、うちのクラスでは無理そう…」
そう感じていませんか?
「時間が足りない」「子どもがバラバラに進んだら混乱しそう」「自分の見取りが追いつかない」——。
多くの先生が、そうした不安を抱えています。
けれど実は、少しの準備で“自由進度”は誰にでもできる学習方法なんです。
今日は、45分の授業の中で少しずつ取り入れられる「5つの準備ステップ」を紹介します。
ステップ① 学習内容を整理する
まず大切なのは、「どこで自由進度を入れるか」を決めること。
最初から単元すべてを自由進度にする必要はありません。
たとえば算数なら「計算練習の部分」、社会なら「調べ学習の部分」だけでもOK。
短い範囲で成功体験をつくることが、継続のカギです。
ステップ② 課題・教材を用意する
自由進度では、子どもが自分のペースで進めます。
そのためには、レベルや目的に合わせた課題を2種類用意すると安心です。
基本課題と発展課題。
「早く終わった子の時間がムダにならない」仕組みをつくることで、全員が集中して学ぶ空気が生まれます。
ステップ③ やることリストをつくる
黒板やプリントに「やることリスト」を見える化しましょう。
今日やること、次に進む流れが分かると、子どもは安心します。
「先生、次は何をすればいいんですか?」が減り、先生も子どももストレスフリー。
自由進度は“放任”ではなく、“自分で進めるための見通しづくり”が大事です。
ステップ④ 学習環境を整える
自由進度では、子どもが自分の課題に集中できる環境が必要です。
タブレットで調べる子、ノートでまとめる子、本で確認する子——。
教室内に選択肢をもてる空間を少しずつ整えるだけで、学びの姿が変わります。
席の配置、掲示物、プリントの置き場所。ちょっとした工夫が、子どもの自立を支えます。
ステップ⑤ 見取りとふり返りを計画する
自由進度では、進度の差だけでなく「学び方」そのものを見取りましょう。
「どんな工夫をして学んでいたか」「どんな困難を乗り越えたか」。
終わったあとにふり返りカードやペア対話を入れると、学びが深まります。
“終わり方”が、次の学びを決めるのです。
よくある疑問💭
子どもが勝手に進みすぎてしまわない?」
→ 見取りと声かけで十分防げます。進んだ子には、友達のサポート役をお願いすると、協働が生まれます。
「ICTがないと難しいのでは?」
→ 紙教材でもOK!ノート・カード・掲示物を使えば、十分に実現可能です。
「授業がバラバラになりそう…」
→ 大丈夫。ゴールは同じでも、そこに向かう道は一人ひとり違っていいんです。
最後に
自由進度学習は、先生の“手放し”から始まります。
最初はうまくいかなくても、子どもが自分で学ぼうとする瞬間を見たとき、
「やってよかった」と必ず感じるはずです。
完璧を目指さなくても大丈夫。
今日紹介した5つのステップのうち、まずは1つから始めてみましょう。
あなたのクラスにも、きっと“自分で進みたくなる子どもたち”が生まれます。
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。